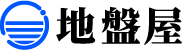地盤改良工法は、建物の安全性と耐久性を確保するために重要な役割を果たします。この記事では、代表的な地盤改良工法の特徴と、メリット・デメリットについて地盤屋なりの経験と実績を元に解説させて頂きます。
1. 表層改良工法
地表から1~2メートル程度の浅い部分の土をセメント系固化材と現地の土をバックホウで攪拌し転圧する方法です。ごく浅層部が軟弱な場合に採用されます。古くからある代表的な地盤改良工法です。
【メリット】
施工が簡単:狭小地や敷地内高低差等があり、 他工法の施工機械が搬入不可な場合でも小型の重機での施工が可能です。地中にコンクリート片や石等の地中埋設物が混入していても対応できます。
【デメリット】
適用範囲が限定的: 地盤の軟弱部分が浅い場合にのみ有効で、地下水位が高い場合には対応できません。
工費が高額になる:施工範囲を建物基礎より0.5m以上拡幅して計画するのが一般的です。他工法と比較して改良率が高くなり、施工費も高くなる傾向にあります。また、多くの固化材を添加するため、それに伴った残土処分費も別途発生します。
施工難易度が高い: 施工者のスキルによって攪拌の仕上がり強度が左右されることがあります。また、近接構造物まで掘削が必要な場合は、土留め等の対策が必要になります。
2. 柱状改良工法
セメント系固化材を水と混ぜてスラリー状にし、現状地盤に注入しながら撹拌することで、地盤を柱状に固化させる工法です。この方法により、軟弱地盤を強化し、建物の荷重を支えることができます。
【メリット】
広範囲に適用可能: 軟弱地盤の深さが2~8mの場合に有効で、支持層がなくても施工できる場合があります
コストパフォーマンスが良い: 比較的リーズナブルで、多くの住宅地盤改良に採用されています。
【デメリット】
固化不良のリスク: 特定の地盤(有機質土など)ではセメントが固まらないことがあります。
将来的な撤去が困難: 改良体の撤去には高額な費用がかかり、土地の売却時に価格が低下する可能性があります。
3. 小口径鋼管杭工法
杭打機で直径80~130mm程度の鋼管を、支持地盤にまで回転挿入して、建物を安定する工法。
【メリット】
高い地盤強度: 施工後の地盤強度が他の工法に比べて高く、重量のある建物にも対応できます。
施工が簡単: 工事期間が短く、狭小地でも施工が可能です。また、残土等が発生しないため現場が綺麗で、養生期間も必要としません。
【デメリット】
高額な費用: 支持層が深い場合には費用が高額になる傾向があります。
4. 砕石置換工法
【メリット】
環境に優しい: 砕石は天然素材であり、有害物質が発生しにくいです。
地盤の安定性向上: 軟弱地盤を強固な砕石に置き換えることで、地盤の安定性が向上します。
資産価値の維持: 砕石を使用するため、将来的に建物を撤去する際に砕石を再利用でき、土地の資産価値を保てます。
【デメリット】
適用範囲が限定的: 新規の盛土造成地や、有機質土地盤(腐植土地盤)の場合は採用できない場合がります。
まとめ
地盤改良工法にはそれぞれメリットとデメリットがあり、建築予定地の条件に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。地盤の専門家に相談し、地盤調査データや地形、ロケーション等を考慮し、最適な工法を選定し、安全で安定した建物を建築することができます。